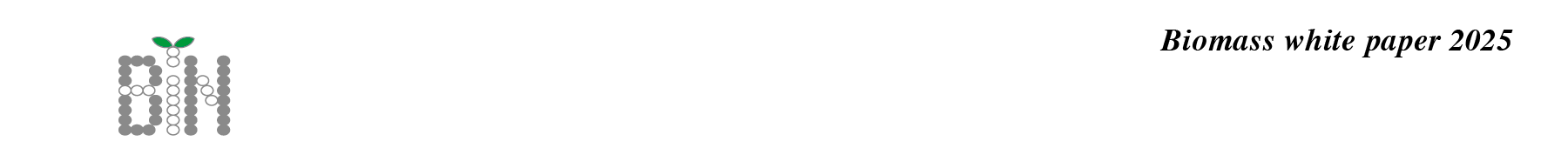










2023年度の日本の温室効果ガス排出・吸収量は約10億1700億CO₂換算tで、前年度比4.2%の減少、2013年度比では27.1%の減少となった【*40】。
令和5年木質バイオマスエネルギー利用動向調査によると、2023年にエネルギーとして利用した木質バイオマスのうち、木材チップの量は1,150万絶乾tとなり、前年に比べ4.0%増加した。そのうち、間伐材・林地残材等が9%増加の492万t、製材残材等が173万t、建築資材廃棄物が391万tであった。

矢野経済研究所は、2030年のバイオプラスチック国内販売量(国内製造、輸入)は約8万tと予測している(図7)【*41】。大手石油精製メーカー各社が廃食油を原料とするSAF製造プラントを稼働する予定だが、副産物のバイオマスナフサがバイオマスプラスチック市場の成長要因となると指摘している。また同研究所では、木粉、デンプン、セルロース繊維、貝殻、卵殻など、バイオマス由来の原料(バイオマスフィラー)を、カーボンニュートラルやバイオエコノミーへの注目から、日用品や玩具、雑貨類などを中心に、従来使用していたプラスチックに高配合し、化石資源由来プラスチックの使用量を削減するという取り組みが進展しているとしている【*42】。

図7:バイオマスプラスチックの国内販売量予測
出所:矢野経済研究所Website
日本は2025年2月、2050年ネットゼロ実現に向けた目標として、2035年度、2040年度において温室効果ガスを2013年度からそれぞれ60%、73%削減することを目指す、新たな「日本のNDC(国が決定する貢献)」を国連気候変動枠組み条約事務局に提出した【*43】。
2025年2月、第七次エネルギー基本計画が閣議決定された【*44】。また2026年度より、排出権取引制度が本格的に開始される。一定量以上のGHG排出企業(CO₂の直接排出量10万t)は、業種等を問わずに一律に参加義務がある【*45】。

2025年4月、長期脱炭素電源オークションの見直しがされ、バイオマスの上限価格は10万円/kWとして、募集上限はないこととなった。また、FIT/FIP 制度において一般木質等(1万kW以上)及び液体燃料(全規模)が2026年度以降の支援対象外となることを踏まえ、同制度においても対象外となる【*46】。

経済産業省は、2030年度までに一部地域における直接混合も含めたバイオエタノールの導入拡大を通じて、最大濃度10%の低炭素ガソリンの供給開始を打ち出した。E20(エタノール20%混合ガソリン)の認証制度についての議論を速やかに開始し、2030年代のできるだけ早期に、乗用車の新車販売にけるE20対応車の比率を100%とすることを目指す。2040年度から、最大濃度20%の低炭素ガソリンの供給開始を追求する。2025年5月には、ガソリンのバイオエタノール導入拡大に向けたアクションプランが示された【*47】。
また、バイオ燃料や合成燃料といった次世代燃料の証書制度「クリーン燃料証書制度」導入の検討が始った【*48】。

環境省は2024年度~30年度、再エネ熱利用・工場廃熱利用等の価格低減促進事業を実施する【*49】。
住宅に関する省エネ基準に適合したプログラムにおいて、主たる居住、その他の居室の「暖房設備機器又は放熱器の種類」の選択肢にペレットストーブが選択された【*50】。日本ペレットストーブ工業会等は、家庭用木質バイオマス燃焼機器の試験方法(JFSA/PSJ-01:2024)を公開した【*51】。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正により、2025年より大麻草の飲食料品類、化粧品などへ産業利用が可能となり、こうした製品の原材料を採取する目的での国内栽培が可能となった【*52】。ただし、事前に栽培者免許を取得する必要がある。
クリーンガス証書制度が始まった【*53】。バイオガスなどをクリーンガスとして設備認定を行い、クリーンガス証書を発行する。

世界各国の有力企業400社以上が加盟し、再生エネルギー電力の利用を進めるRE100が、2025年4月、調達基準を規定する技術要件を改定し、石炭混焼による電力を使用禁止とした【*54】。また、RE100ではバイオマスから生成された再生可能電力をRE100目標に計上する場合、ISCCやGreen-e®Energy認証などの適切な持続可能性を保証するものの取得を条件としている【*55】。
2024年7月、秋田県大潟村で籾殻を燃料とするバイオマス熱供給事業が開始された【*56】。村内で大量に発生する籾殻をデンマークのLinka Energy A/S社製バイオマスボイラーで燃やし、デンマークのLOGSTOR INTERNATIONAL Sp.z o.o.社製熱導管で宿泊施設、温浴施設、福祉施設、小中学校5カ所に熱供給を行う。
山形県長井市の那須建設は、民間よるエネルギーサービス事業として、温泉施設や福祉施設へのチップボイラー導入を行っている【*57】。バイオマスボイラーは同社が設置・運用し、エネルギーを販売している。
日比谷アニメスは、温風ファンユニット「HFU」を開発し、極東開発工業の木質チップ乾燥コンテナ「Kantainer®」と組み合わせて焼却炉の排熱でチップを乾燥させるシステムを、安田クリーン産業に納品した【*58】。

写真:HFUとKantainer®接続の様子
(写真提供:日比谷アメニス)

産業総合研究所は、排熱を利用した発電ができるバイオ炭生産システムの設計コンセプトを確立した【*59】。
日本サーモエナーは1.2t/hの木質バイオマス蒸気ボイラ「BSU-1200N型」を販売開始した【*60】。
千葉ステーションビルは、2025年4月、ペリエ海浜幕張で、同社が運営する他の施設から排出される食品廃棄物由来のバイオガス発電と環境価値を還元供給する取り組みを開始した【*61】。
大成建設と伊藤忠エネクスは、軽油に代わる新燃料RD40の使用を開始した【*62】。RD40は、廃食用油等のバイオ起源の燃料を40%含んでいる。
三菱ガス化学は、2024年6月、新潟市に消化ガスを原料とするバイオメタノール製造設備が完成し、製造を開始した【*63】。レゾナックおよび丸紅とNesteは、レゾナック大分コンビナートで2024年6月より、エチレンやプロピレンなどにバイオマス原料の使用を開始した【*64】。

愛媛県内子町にある内子バイオマス発電所では、木質ペレットを燃料とする木質バイオマスガス化発電を行っている。燃料となる木質ペレットを製造する際に、樹皮を燃やして乾燥を行うが、その際に発生する灰は、セメントなどを加えて、バイオマスストーンとして再生され、林道の舗装などに活用されている【*65】。
東京エネシス子会社の境港エネルギーパワーは、境港バイオマス発電所から発生する焼却灰を原料とした肥料を試作した【*66】。

九州バイオマスフォーラムは、2024年9月~10月にかけて九州バイオマスツアーを開催した。シンポジウム、バイオマス熱利用、発電所、バイオマスプラスチック工場など7カ所の視察、ミニ講演会と充実した内容で、170ページの講演録・資料も作成された【*67】。
2025年5月に開幕した大阪万博会場日本館には、会場内から回収した生ごみを発酵させるバイオガスプラントが併設されており、そこで発電した電力を日本館で活用している【*68】。
2050年カーボンニュートラルに向けて国際的な取り組みが進むなか、化石燃料に頼ってきた航空分野における持続可能な航空燃料(SAF)に関わる動きも活発になっている。
国際民間航空機関(ICAO)は、2024年以降のCO₂排出量を、2019年時点の85%未満に抑える目標を採択し、2023年の会合で「2030年までにSAF等の利用により、5%の炭素削減を目指す」といったグローバルな中間目標が設定された。
ICAOは、SAFのGHG排出量削減基準等の証明に、CORSIA適格燃料認証を求めている。この認証を取得するためには、ICAOが承認した持続可能性基準スキーム(SCS)への認証取得の申請が必要である。持続可能性基準には、温室効果ガス、炭素ストック、GHG排出削減の永続性、水、土壌、大気、生物多様性保全、廃棄物及び化学物質、地震及び振動の影響、人権及び労働者の権利、土地利用の権利及び土地利用、水利用の権利、地域及び社会の発展、食料安全保障の各テーマに原則と基準が設けられている。現状でISCC、RSBおよびClassNKの3つの持続可能性認証スキーム(SCS)がある【*69】。

2023年5月、経済産業省はSAF官民協議会(第3回)において、「国内における2030年のSAF供給目標量を航空燃料消費量の10%(172万KL相当)」とする方針を提示した【*70】。エネルギー供給構造高度化法においてSAFの供給目標量を設定し、対象期間は2030年~34年度、対象事業者は年間10万KL以上のジェット燃料製造・供給事業者とする。GHG排出基準は定めないが、努力規定として対象事業者にGHG削減効果50%を目指すことを求める、としている。

図8:SAFの利用量・供給量の見通し【*70】

こうした動きを受けて、石油元売り企業や製紙会社等は次々にSAF製造施設の計画を進めている。製紙会社では、王子ホールディングス、日本製紙、大王製紙、レンゴー、丸住製紙などが、古紙や建築廃材、木質チップからバイオエタノールを製造し、SAFに加工する(表3)。

表3:製紙会社のバイオエタノール生産に関わる取り組み

| 王子HD | 約43億円を投じ24年度に鳥取県で実証設備稼働。年産は当初1000KL 、30年目標は10万KL |
|---|---|
| 日本製紙 | 住友商事、GBIと27年度から年産数万KL。投資は数百億円規模か |
| 大王製紙 | 古紙を使うGEIとの共同事業をNEDOが採択 |
| レンゴー | 子会社がNEDO採択。Biomaterial in Tokyoと組廃材から年産2万KL。事業規模約95億円 |
| 丸住製紙 | パルプ工場として世界初のISCC-CROSIA認証を取得 |
出所:日刊工業新聞 2024年2月29日付および報道資料

SAF原料としてはその他廃食油、バイオエタノール、非食用ココナツオイル、ポンガミア油などが挙げられている。日揮は、家庭や店舗から出る廃食油からSAFをつくるFry to Fly Projectを始めている【*71】。廃食油はGHG排出が低い国産資源だが、利用可能量が少ないため、それ以外の環境負荷の低い原料をどう調達していくかが、大きな課題となる。
液体燃料は船舶や建機燃料としても需要があり、脱炭素に取り組む各企業の取り組みが進められている。




